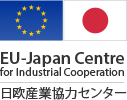
再生可能エネルギーの大規模展開は、日欧が2050年までに実現を目指している「気候中立」に向けて鍵となる活動です。欧州委員会は、2050年までにヨーロッパの電力需要の30%が洋上風力発電で賄われる可能性があると推定しており、また日本政府は洋上風力発電を新しいグリーン成長戦略の柱に据えるなど、洋上風力発電は、日欧両地域において最も成長可能性が高い再生可能エネルギー源の1つと見なされています。
洋上風力発電に関し、世界のタービンメーカー上位5社のうち3社がEUに拠点を置いており、世界市場の90%を占めるのはEUの企業です。その中で日本は、2040年までにEUと中国に次ぐ第3位の生産国になることを目指しています。こうした洋上風力発電に関する動きは、日欧企業間の協力をさらに加速させ、より費用対効果の大きい活動に繋がることが期待されています。そして日欧企業間の協力を深化させるためには、各企業が互いに知識を深め、各国の認証システムをよりよく理解する必要があるといえます。
本イベントでは、日欧企業協力の成功例を取り上げたほか、(1)洋上風力技術の認証と適合性評価システム(2)浮体式洋上風力のコスト削減、の2つに焦点を当て、日欧双方の企業が知識を深め、協力促進の一助となることを目的に実施しました。
まとめ
日欧の洋上風力発電の公共政策と産業開発
認証と適合性評価について
開会の挨拶内にて、欧州委員会のフロリアン・エルマコーラ氏は、EUにおける今後2050年までの洋上風力エネルギーへの関心の高さと課題について述べるとともに、洋上風力発電の導入の持続的な増加による雇用創出の可能性について指摘しました。
2020年に発表された洋上再生可能エネルギーに関するEU戦略では、投資の円滑化、地域協力の促進、オークションの計画、イノベーションの支援、サプライチェーンの確保を強調するEUの法的枠組みが示されています。
エルマコーラ氏は、ドイツやオランダでは補助金なしの入札などの政策によりオークション価格が低下していることから、洋上風力発電の競争力が高まっている、と述べました。
政策面の適切な枠組みと優れたオークション基準に基づいた競争が行われていけば、イノベーションは動き出すでしょう。
欧州委員会エネルギー総局 隣国政策・国際関係部長 フロリアン・エルマコーラ氏
経済産業省の小山 雅臣氏より、2019年の新たな法律の制定から2020年の日本の洋上風力発電ビジョンの提示に至るまで、日本の洋上風力政策の最新動向をご紹介いただきました。日本は洋上風力発電を、2050年までに炭素排出量をゼロにする道筋を支える「グリーン成長戦略」の柱として位置づけており、洋上風力発電の産業的発展は、環境保護と経済の好循環を示すものと考えられます。小山氏は、洋上風力発電における日本の産業競争力を強化する意向を示し、欧州企業とのさらなる協力関係の構築に意欲を示しました。
洋上風力発電は、日本がカーボンニュートラルを目指す上で
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部国際室長
不可欠な柱の一つ。
欧州風力協会CEOであるジールス・ディクソン氏からは、欧州の洋上風力発電産業の現状と今後の動向をご紹介いただきました。国際エネルギー機関(IEA)によると、2040年頃から欧州の電力供給源の第一位は洋上風力発電になると言われています。しかし、現在、洋上風力は欧州の電力消費量の3%に過ぎません。2030年までに洋上風力発電の容量は5倍に増加し、洋上風力発電業界では約30万人の雇用が見込まれています。2014年から2019年の間にオークション価格が75%低くなっていることから、導入規模が増えれば増えるほどコストが下がっていると共に、CFD(差金決済)取引などの政策もコスト低下に活用できている、と指摘しました。
洋上風力発電の導入が早ければ早いほど、コストは下がります。
欧州風力協会 CEO ジールス・ディクソン氏
日本風力発電協会(JWPA)理事の片山 仁氏からは、経済産業省が2020年に宣言した実施目標を受け、日本における洋上風力発電の展望と役割を述べていただきました。日本は実施目標達成のために、国内市場の魅力を高め、投資を促進し、規制の枠組みを見直し、適切な技術を開発するために、官民の取組みが構築されています。片山氏は、日本は金融面・産業面における基盤できているものの、ノウハウや技術、経験が不足していることから、日本の洋上風力発電産業の発展のために欧州企業と協力して強固な基盤を築いていきたい、と述べました。
基盤はしっかりできているが、ノウハウや技術、経験は少し足りない。
一般社団法人 日本風力発電協会(JWPA)理事 片山 仁氏
ヨーロッパの企業や専門家から学び、彼らと手を携えていくべきです。
上記4つのプレゼンテーションの後、司会者のソニア・ヴァン・レンセン氏が登壇者へのQ&Aセッションを開始し、入札プロセスについての意見を共有しました。
洋上風力発電をスケールアップしていくにあたり、入札はどのように役立つのか、EUと日本の入札プロセスにはどのような違いがあるのか、また、EUと日本の両方に適用できる理想的な基本原則は何か、等について議論しました。
アンドリュー・ホー氏(Orsted/ アジア太平洋地域新興市場・政府規制対策室長)より、日本でのプロジェクトにおける同社の経験について簡単にご説明いただきました。2020年3月、Orsted社と東京電力株式会社(TEPCO)は、銚子市の洋上風力発電推進地域での共同入札に向けて、合弁会社を設立しています。ホー氏は、日本と新市場全体のための新しい早期パートナーシップモデルを紹介し、プロジェクトの開発段階で適切な経験豊富なパートナー得ることで、予算内で計画通りにプロジェクトを進めていくことができる、と述べました。
日本のような新しい市場では、早い段階で参入し、
Orsted アジア太平洋地域新興市場・政府規制対策室長 アンドリュー・ホー氏
共に協力して適切な関係を築くことに大きな価値があります
続いて、住友商事を代表し、梁井崇史氏より欧州における洋上風力発電事業の概要についてプレゼンテーションを頂きました。現在、住友商事は欧州での計9件のプロジェクトを実施しており、欧州市場でのコネクションを確立しています。梁井氏は、今後洋上風力発電の市場を拡大していくにあたり、欧州企業との強力なパートナーシップは不可欠であることから、良好な協力関係を築いていきたいという展望を述べました。
欧州企業との強力なパートナーシップは不可欠。
住友商事株式会社 電力インフラ第2部長 梁井 崇史氏
今後とも良好な協力関係を築いていきたい
本セッションでは、日本企業2社と欧州企業2社にご登壇いただき、洋上風力発電に関する最新のソリューションを紹介していただきました。
入江悦郎氏(日本精工株式会社(NSK))より、風力発電機用の軸受、軸受の故障に対するソリューション、洋上風力発電機の技術サービスについてご説明いただきました。
タービンメーカーであるSiemens Gamesa社のシニアプロダクトマネージャー、ピーター・J・H・エスマン氏は、ダイレクトドライブテクノロジーに関する漸進的学習プロセスを紹介するとともに、Siemens Gamesa社製品の3つの主な特徴(ナセル内の変圧器設置による迅速なタービン設置の実現・永久磁石式ダイレクトドライブ発電機により、風車内にギアボックスを設置する必要がないこと・他社と比較して軽量なインテグラルブレード)について述べました。
前田俊介氏(三菱電機株式会社 エネルギーシステムソリューション部)より、洋上風力発電におけるエンジニアリング、製品開発、技術サービスの取り組みをご紹介いただくとともに、三菱電機が提供している、日本の送配電網の革新的な運用をサポートするパッケージソリューション「BLEnDer(ブレンダー)」についてご説明いただきました。
続いて、海運会社Van Oordのアジア向け洋上風力発電事業部長であるクー・ヴァン・オード氏より、同社が日本市場に導入したいと考えている2つの具体的なイノベーション(スリップジョイント接続による軽量化・スカワ保護による基盤周辺の生態系保護)について述べていただきました。
マーティン・ウェブホーファー博士(TÜV SÜD グリーンエネルギー・持続可能性事業部マネージャー)により、プロジェクト認証の目的と範囲についてご説明いただきました。第三者機関による認証・評価は、風力発電に限らず、さまざまな側面や関係者が関わっていることに言及しました。
ベン・ウォルドロン氏(DNV エネルギーシステム 台湾・日本エリアマネージャー )は、 マーティン・ウェブホーファー博士プレゼンテーション内容を踏まえ、新しい市場への洋上風力発電の普及をサポートするためにどのように適応させることができるかに焦点を当て、認証機関と国際規格によるリスク低減についてお話いだだきました。
日本からはまず、 赤星 貞夫氏(日本海事協会(ClassNK) 事業開発本部 環境・再生可能エネルギー部)より、日本での洋上風力発電計画に関わる法令をご説明いただくとともに、各手続きにおいて、必須となる証明書の種類と、ClassNKのサービスがどのような状況で適用されるかについてのご説明をいただきました。
橋本淳氏(日本電機工業会(JEMA)技術戦略推進部)は、機器の標準化を図り国際的に分業することが、洋上風力発電の競争力強化に繋がると主張するとともに、生産者の潜在可能性を引き出すためにオープンソースのプラットフォームを推進し、発電機、コンバータ、増速機、軸受、異業種からの参入を促していくことを明言しました。
そして最後に、福永 勇介氏(沿岸技術研究センター(CDIT) 研究主幹)に、洋上風力発電施設の係留設備の適合性確認業務についてご説明いただきました。
続いて行われたパネルディスカッションでは、日欧の認証機関5社に加え、Orsted・三菱電機の2社にご登壇いただき、洋上風力発電の費用対効果の高い導入を可能にする適合性評価の役割、国内規格と国際規格の整合性、日本とEUのさらなる交流などについて意見を交えていただきました。
浮体式タービン:洋上風力発電の新たな可能性を開拓するために
協力とコスト削減の展望
Stiesdal Offshore Technologies社CEOであるヘンリック・スティーズダル氏の主なメッセージは、浮体式洋上風力発電に対する産業的なアプローチが現在欠けているということでした。洋上風力発電プロジェクトのコストを決定する主な要因は、規模の経済であることが明らかになっています。しかし、浮体式洋上風力発電機の設計・製造には、労力とコストがかかるのが現状です。そのため、スティーズダル氏は、洋上風力発電機の競争力を高めることを目的とした、Tetraと名付けられたモジュール式洋上風力発電機のコンセプトを紹介しました。さらに、2020年には欧州でのTetraSper実証プロジェクトに東京電力と協力している等、プロジェクト実現には日本が深く関わっていると述べました。
NEDOの洋上風力開発事業の取り組みについて、新エネルギー部の佐々木 淳氏より着床式と浮体式の両面についてご説明いただきました。また、NEDOの洋上風力発電情報閲覧システム「NEOWins」の目的と成果、2014年から進めている浮体式洋上風力発電システム「ひびき」の実証実験についての現状、そして洋上風力の産業競争力強化に向けた技術開発ロードマップについて説明し、諸外国の特徴と日本の技術開発を鑑みた上で、今後日本ではロードマップに沿った形で技術開発が進んでいくとの見通しを述べて頂きました。
Engie社とEDPR社の合弁会社であるOceanWinds社Ocean Windsを代表して、ペライヨ・ロドリゲス・アロンソ氏にご登壇いただき、同社が欧州委員会と欧州投資銀行の支援を受けてポルトガルで実施した洋上風力発電プロトタイプ「WindFloat 1」の商業化前プロジェクトの概要をご説明いただくとともに、これらの経験を踏まえ、日本で同様のプロジェクトを行う際の4つの主な課題として、信頼できるサプライチェーンの構築、フローターの最適化、台風に耐えうるような設置方法、電気インフラと連結系統という4点を挙げるとともに、日本側での主要な優先事項として、コスト削減、サプライチェーンのローカル化と雇用創出、漁業や地域社会との共存、という3点をご指摘いただきました。
日本は世界第3位の市場になるだろう
Ocean Winds 事業開発統括マネージャー
ペライヨ・ロドリゲス・アロンソ氏
JERAの矢島聡氏からは、台湾、イギリス、日本での洋上風力発電事業について詳しくご説明いただきました。JERAは、2025年までに自然エネルギーと液化天然ガスの分野でグローバルリーダーになるという目標を掲げており、その達成のため、海外での入札や洋上風力発電事業に積極的に取組むことで洋上風力発電の建設・運営両方の知識と経験を積んでいます。また、浮体式洋上風力発電のポテンシャルと現状の課題(国内のサプライチェーン不足、係留システムの改善、製造の効率化、利害関係者(特に漁業関係者)からの理解と信頼を得ること、系統容量の増加)について述べて頂きました。
欧州の事例から、真摯に学んでいきたい
株式会社JERA 執行役員 事業開発副本部長 矢島 聡氏
技術力の高い企業を代表し、BW Ideolのブルーノ・ゲッシャー氏にご登壇いただきました。BW Ideolは、ヨーロッパとアジアという2つの戦略的地域で2つのフルスケール浮体式洋上風力発電機を運用しており、JERAを初めとした日本企業ともパートナーシップを結んでいます。ゲッシャー氏は、フランスと日本の洋上風力発電事業の経験を踏まえ、製造する素材はコンクリートの方が鉄鋼よりも安価でコスト競争力が高く、地元の雇用を創出することが可能だと指摘すると共に、日本企業は、貴重な知識と経験を持つヨーロッパの中小企業とパートナーシップを築くことに熱心であると述べました。
ジャパンマリンユナイテッド(JMU)の吉本治樹氏に、造船から研究開発、そして1999年からは浮体式洋上風力発電にも取り組んでいる同社の活動をご紹介いただきました。中でも、経済産業省の実証研究開発プロジェクトとして、福島で4基中3基の浮体式風力発電機を開発・設計・建造・設置に携わった経験は、同社にとってターニングポイントとなったと述べています。この経験を踏まえ、現在は商業化・産業化を目指した新世代のセミサブ型のコンセプトを打ち出しており、浮体式洋上風力発電機の製造においては、コスト競争力、信頼性、製造のしやすさの3つのバランスを取ることが重要、とご指摘いただきました。
2-B Energy社CEOのハーバート・ピールズ氏から、同社の2BE技術をご紹介いただきました。同技術は、2枚羽ローター、ダウンウィンド・オリエンテーション、パッシブ・ヨーという3つの革新的な技術で構成されています。また、オランダでの2B6タービンの建設により、建設・管理に関する経験と知識を得たと述べていただきました。
東京製綱株式会社を代表し、守谷 敏之氏に、同社製品の開発実績をご紹介いただきました。同社製品の強みとして、スチールや炭素繊維等さまざまな素材のロープを提供できる点、耐腐食性、洋上風力発電機の係留、船舶への搭載等の経験を有する点などを挙げていただきました。また、日本では急に水深が深くなる場所も多く係留コストがかかる点についての問題点を踏まえ、積極的にシステム提案をしていきたいとの展望を述べて頂きました。
浮体式洋上風力発電のサプライチェーンを構成する80社以上の企業を代表する欧州風力協会社のリゼット・ラミレス氏より、2030年にヨーロッパで7GWの浮体式洋上風力発電を実現する方法をご説明頂きました。規模の経済が重要な役割を果たすことから、達成の為には工業化と大量生産が必要であると断言し、そしてヨーロッパの浮体式洋上風力発電には、まだまだ大きな可能性があると述べました。
世界風力会議(GWEC)のヘンリック・スティーズダル氏は、今後20年間、風力発電市場が成長し続けることを示唆しました。GWECのビジョンを確立する上で、日本は重要な市場であり、成長可能性とニーズを有する点を強調しました。こうした状況を踏まえ、GWECは現在、日本風力発電協会(JWPA)とともに、日本の洋上風力発電の大きな可能性を引き出す上で障害となっている規制上のボトルネックを解決することを目指しており、各種ステークホルダーと共に、ベストプラクティスの共有や研究の実施、関係者間の協力体制の強化などを行っていると述べました。
経済産業省の柳田康介氏より、洋上風力発電の開発に関して日欧双方が高い目標を掲げていることに触れ、洋上風力発電における今後の協力関係の強化が不可欠であること、そして欧州委員会エネルギー総局のマチュー・クレイエ氏より、コスト削減、透明性、公共調達などのいくつかのテーマについて、欧州と日本の間でさらなる交流の可能性がある点についてお話いただき、閉会となりました。